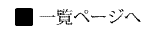型紙が余分に必要だし、裏地っでツルツル滑って縫いにくそうだし、「難しそう」と感じるのも無理はありません。
では、裏地付きの洋服の方が仕立てるのが難しい、または手間がかかるかと言うと、多くの場合はその通りですけど、例外はあります。
完成した洋服の裏側の美観を全く気にしないのなら、裏地を付けない方が、単純に楽で簡単です。
「表から見てキレイなら、裏側は気にしない」と考えても構いませんが、裏側を気にするなら、裏地を付けた方が簡単なことはあります。
「臭いものに蓋をする」ように、まとめて縫い代を隠せるからです。
一般論としては、洋服の構造が単純なら裏地はない方が簡単ですが、構造が複雑になるにつれ、裏地を付けてしまった方が、かえって簡単になることがあり、裏地を付けない方が難しいと思うものの一つとして、「箱ポケット」があります。
そこで今回、作ってみたのですが、自分では、裏地のない仕立て方での箱ポケットは作ったことはなく、売っている洋服で見た記憶もないので、さすがに「世界初」という訳ではないでしょうけど、珍しいと思います。
※ここをクリックすると、作品のページに移動します。
 1.
1.
写真【2】は、表から見た箱ポケット、写真【3】が裏側から見たところで、初めて作ってみた感想としても、やはり裏地のない仕立てのほうが難しく、なれない人にはオススメはできません。
具体的に裏地がない服の箱ポケットが、どう難しいかという話は割愛しますが、仕立てるときの美観について、4つの「面」に分けて考えると良いのではないか思います。
 2.表から見た箱ポケット
2.表から見た箱ポケット 3.裏から見た箱ポケット
3.裏から見た箱ポケット
写真【4】の表から見える面を「A面」、写真【5】の裏返して見える面を「B面」、「C面」は、この状態では見えないけど、生地と生地の間を覗くと見える面で、今回の場合は、袋布の裏側がそれにあたり、裏地のない身返しの裏側や、「ふらし仕立て」の表地と裏地の間、などがあります。
最後の「D面」は、糸や生地を切らない限り見えてこない面のことで、ここでは身返しの裏側、他にも一般的な裏地のある服の表地と裏地の間、などがあります
A面はデザインそのものなので、それぞれの服によって違うことは当たり前ですが、B面・C面をどこまで気にするかの考えは、時代によっても違いがあり、例えば最近は、通常「ふらし仕立て」の服の縦の縫い代にはロックミシンがかかっていますが、昔の服の多くは断ち切りのままでした。
D面は全く見えないので、特に気にしなくても構わないのですが、後で修理が発生することを想定して、事前にキレイに整えておく場合はあり、また、作り手のコダワリを込めることもあります。
 4.
4. 5.
5.
実際に仕立てるときの優先順位は、通常は、A面>B面>C面>D面、となりますが、裏側をキレイに見せるために、表の美観を犠牲にすることもあります。
この服は、全ての縫い目が、「袋縫い」という方法によって、裏から見てキレイに見えるように仕立てましたが、表からの美観のみを考えるなら、ロックミシンをかけただけの方が、薄く柔らかく仕上がり、どのように仕立てるかは生地の厚さ(硬さ)などによって判断が異なります。
また、どの面にどれだけの美観を求めるかには、手間(コスト)の制約もあります。
「かえって、裏地を付けた方が簡単」というのは、B面をキレイにすることが難しいケースで、裏地があることによって、B面を、C面・D面と同列に扱えるからです。
また、今回のような洋服の構造によるもの以外にも、メンズジャケットのように広い面積に「芯」を貼っているケースや、ジャガード生地のような裏側に織糸が露出しているケースなどは、裏地を付けない仕立て方には適しません。
裏地を付ける・付けないの選択は、着心地や、暖かさなどの裏地自体の機能とともに、それぞれの仕立て方に適したデザインや、B面の美観などを、総合してして検討することが必要になります。