ボクの場合は主に、「先に形を考え、それに合う生地を探す」場合と、「先に使う生地があり、それに合う形を考える」場合の2つに分かれ、生地をつくる人は、これらとは異なる過程になりますが、多くの人にとって、同じように分かれるのではないでしょうか。
ただ実際には、これほど単純なわけではなく、たとえば「先に形を考え、それに合う生地を探し、その生地に合うように形を修正する」など、複合的なケースはたくさんあります。
形を考える過程も、主に2つのパターンに分かれ、「先に全体の形を考え、それに合うディテールを考える」場合と、「先に採用したいディテールがあり、それに合うように全体の形を調整する」場合があり、こちらは、後者の工程ではつくることのない人はいますし、自分でも後者の工程でつくる機会は少ないです。
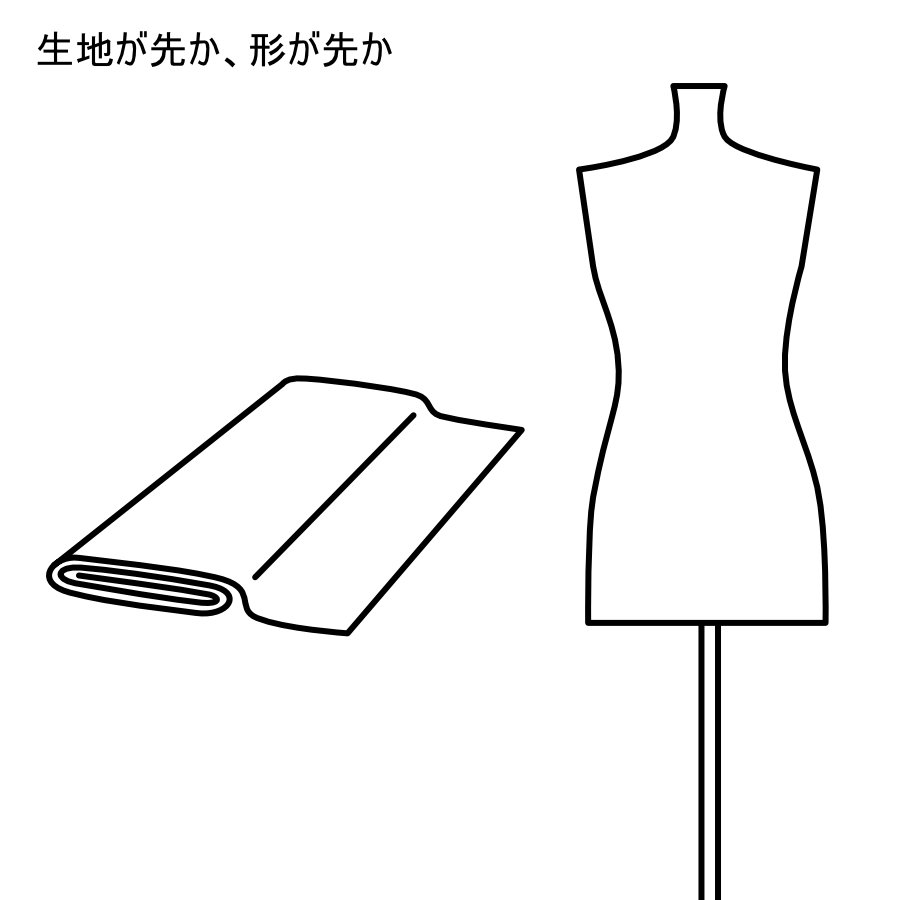 1、生地が先か、形が先か
1、生地が先か、形が先か
ここで、これらの「マトリクス図」をつくり、個人的な事例に即して、それぞれの過程に名前をつけました。
※他の人にとっては、「私には、他の名前のつけ方が相応しいと思う」ということがある、と思います。
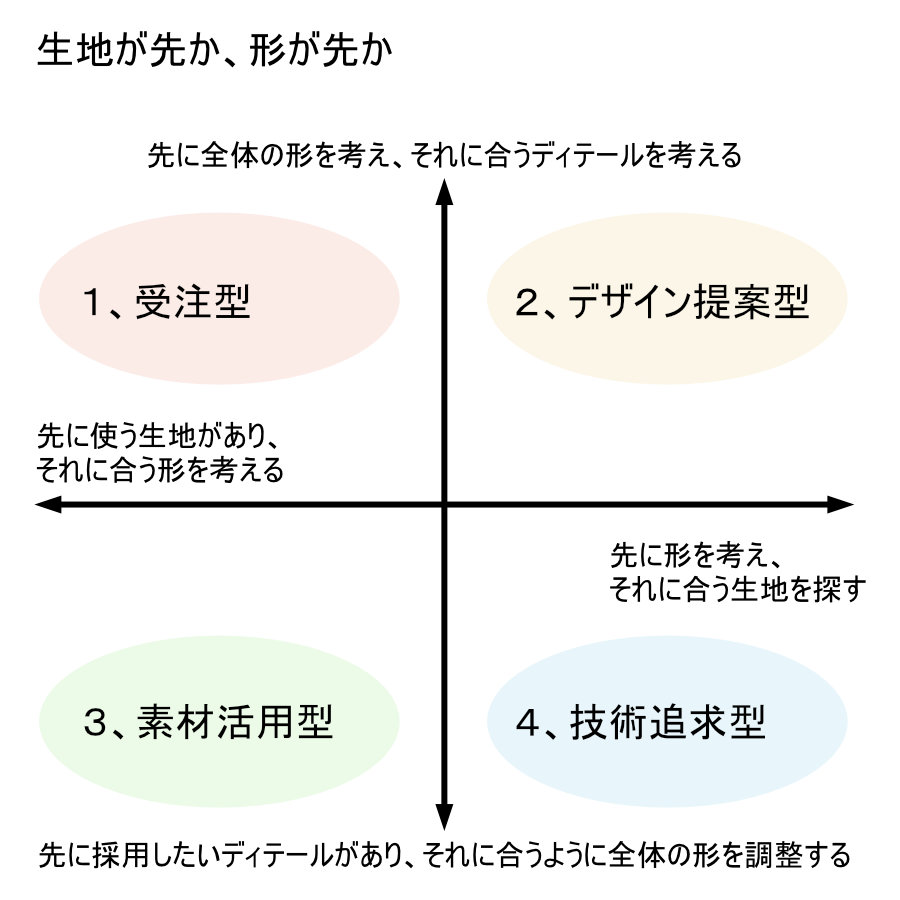 2、マトリクス図
2、マトリクス図
1、受注型
ボクのオーダーメイドの服つくりの多くは、この過程になります。
2、デザイン提案型
あえて、オーダーメイドではやりにくい形のデザインは、この過程でつくることがあり、自分の着る服をつくる場合は、1と2が半々くらいで、なかなか機会はありませんが、一部3、4があります。
3、素材活用型
プリントなどの生地で、その柄の特性を積極的に活かしたりするときなど、この過程でつくることもありますが、機会は少ないです。
4、技術追求型
ボクの服つくりにおけるミッションの一つに、「服つくりを進歩させたい」ということがあり、そのためにも、この過程でつくることには積極的なのですが、これも機会は少ないです。
これらの区分けは、状況によって必要とされることが異なり、それに対応することになりますが、分けて考えたほうが良い理由として、「この過程の違いにより、デザインが変わる」ことがあり、以下に、それぞれの特徴の例を挙げました。
1、受注型
先に素材があるので、予想外のものにはなりにくいけど、予想を超えたものにもなりにくい。
複数の生地を使うデザインには、比較的不向き。
2、デザイン提案型
1と逆の傾向。
3、素材活用型
全体のデザインが平凡になりがち。
4、技術追求型
形をまとめるのが難しい。
「先に採用したいディテールがあり、それに合うように全体の形を調整する」という過程を想定することは、それ自体が必要ないと思うかもしませんが、細部が服つくりを決めることもあります。
また、つくる服のデザインとの相性や、作り手によっての得意不得意があり、必ずしも無理をして不得意な過程でつくる必要はありませんが、「デザインは過程に制約を受ける」ことは自覚しておきましょう。
